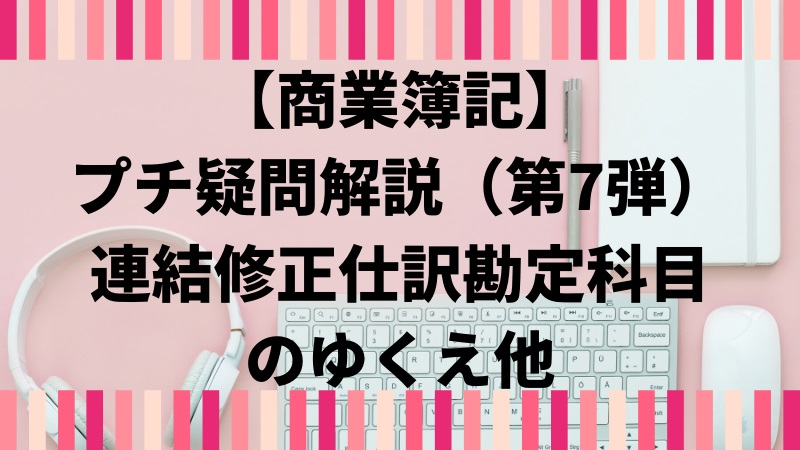本記事では
- 連結修正仕訳だけに使われる勘定科目の総見直し
- 「非支配株主に帰属する当期純利益」から「非支配株主持分当期変動額」への振り替えの意味
について解説します。
それでは、まいりましょう。
連結修正仕訳だけに使われる勘定科目の総見直し
連結修正仕訳の時だけ使う勘定科目について総復習しましょう。
例えば、次の太字の部分が連結修正仕訳のときだけ使う勘定科目です。
投資と資本の相殺消去
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 資本金 | 8,000 | S社株式 | 8,000 |
| 利益剰余金 | 2,000 | 非支配株主持分 | 3,000 |
| のれん | 1,000 |
子会社の当期純損益の振り替え
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 1,000 | 非支配株主持分当期変動額 | 1,000 |
子会社の配当金の修正
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 受取配当金 | 700 | 剰余金の配当 | 1,000 |
| 非支配株主持分当期変動額 | 300 |
投資と資本の相殺消去に関する開始仕訳
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 資本金当期首残高 | 4,000 | S社株式 | 8,000 |
| ...(割愛)... | ...(割愛)... | ...(割愛)... | ...(割愛)... |
前期以前の連結修正仕訳ののれん償却分の開始仕訳
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 利益剰余金当期首残高 | 200 | のれん | 200 |
連結修正仕訳だけに使う勘定科目(上の太字部分)の処理方法について解説します。
step
1損益計算書への展開
費用・収益勘定を損益計算書へ展開
step
2株主資本等変動計算書へ展開
- 損益計算書の当期純利益を株主資本等変動計算書に展開
- 純資産勘定を株主資本等変動計算書に展開
step
3貸借対照表へ展開
株主資本等変動計算書の金額を貸借対照表へ展開
では勘定科目単位で確認していきましょう。
連結修正仕訳用の勘定科目と連結財務諸表の関係
| 勘定科目 | 区分 | 単独で関係する連結財務諸表 |
| ①非支配株主に帰属する当期純利益 | 費用・収益 | 「損益計算書」の金額を「株主資本等変動計算書」へ記載 |
| ②親会社株主に帰属する当期純利益 | 費用・収益 | 「損益計算書」の金額を「株主資本等変動計算書」へ記載 |
| ③非支配株主持分当期変動額 | 純資産 | 株主資本等変動計算書 |
| ④剰余金の配当 | 純資産 | 株主資本等変動計算書 |
| ⑤利益剰余金当期首残高 | 純資産 | 株主資本等変動計算書 |
| ⑥資本金当期首残高 | 純資産 | 株主資本等変動計算書 |
| ⑦非支配株主持分 | 純資産 | 株主資本等変動計算書 |
②親会社株主に帰属する当期純利益は連結修正仕訳ではでてきません。
連結損益計算書でグループ全体の当期純利益から上の非支配株主に帰属する当期純利益を差し引いた金額です。
勘定科目の組み合わせで関係する連結財務諸表
⑦非支配株主持分+(①非支配株主に帰属する当期純利益+③非支配株主持分当期変動額) → 貸借対照表
⑤利益剰余金当期首残高+(②親会社株主に帰属する当期純利益+④剰余金の配当) → 貸借対照表
⑥資本金当期首残高+(株式発行などによる資本金当期変動額) → 貸借対照表
「非支配株主に帰属する当期純利益」から「非支配株主持分当期変動額」への振替の意味
連結修正仕訳で次のような仕訳をみかけますよね。
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 〇〇〇 | 非支配株主持分当期変動額 | 〇〇〇 |
- 「非支配株主に帰属する当期純利益」は損益計算書の勘定科目(当期純利歴)
- 「非支配株主持分当期変動額」は株主資本等変動計算書の勘定科目(純資産)
この振り替えはもうけから純資産への振り替えです。
例えば、個別決算では損益を純資産の繰越利益剰余金へ振り替えます。
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 損益 | 〇〇〇 | 繰越利益剰余金 | 〇〇〇 |
上の個別決算の仕訳の借方、貸方、それぞれを次のように置き換えると、(借)非支配株主に帰属する当期純利益、(貸)非支配株主持分当期変動額となります。
・「損益」→「非支配株主に帰属する損益」→「非支配株主に帰属する当期純利益」
・「繰越利益剰余金」→「非支配株主持分当期変動額」
「非支配株主に帰属する当期純利益」を「非支配株主に帰属する損益」と読み替えれば、個別決算時の当期純利益から繰越利益剰余金への振り替えと同じなんですね。

『非支配株主に帰属する当期純利益』ではなく、『非支配株主に帰属する損益』にしてほしかったですねぇ(笑)