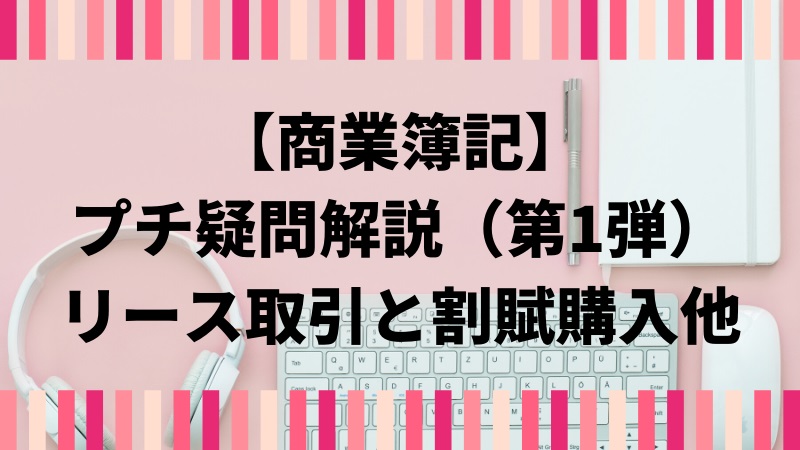本記事では
- ファイナンスリース取引と割賦購入の仕訳方法
- 手形と小切手の仕訳方法
について解説します。
リース取引と割賦購入の利息の違い
ファイナンスリース取引と割賦購入では利息分の仕訳方法が異なります。
実際の問題を使って解説します。
最初に割賦購入時の利息分の仕訳について
割賦購入時の利息の仕訳方法
備品60,000円を3ヶ月分の分割払い(月々の支払額は21,000円)の契約で購入した。
この時の仕訳を行いなさい。
解答を解説します。
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 備品 | 60,000 | 未払金 | 63,000 |
| 前払利息 | 3,000 |
割賦購入時の利息分は前払利息(資産勘定)になります。
その後、利息分を支払う時は前払利息(資産勘定)を支払利息(費用勘定)に振り替えます。
次にリース契約時の利息分の仕訳について
ファイナンスリース契約の利息の仕訳方法
当期の4月1日に備品のリース契約を年間のリース料21,000円(毎年3月末日払い)、期間3年の条件で契約した。
リース料の総額は63,000円、現金で購入した場合の価格は60,000円である。
契約時の処理について、利子抜き法で仕訳を行いなさい。
解答を解説します。
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| リース資産 | 60,000 | リース債務 | 60,000 |
ファイナンスリース契約時は利息分はまだ仕訳しません。
利息分は実際に支払った時に支払利息(費用勘定)で仕訳します。

割賦購入の利息は前払利息で計上していたけど、ファイナンスリースでは計上しないんだな
ファイナンスリース契約と割賦購入では、はじめの利息の仕訳方法が異なります。
・割賦購入では利息分は前払利息(資産勘定)で計上
・ファイナンスリース契約(利子抜き法)では何もしない
手形と小切手の違い
商業簿記でよく出てくる手形と小切手。
「手形を振り出した。」
「手形で受け取った。」
「小切手を振り出した。」
「小切手で受け取った。」
手形と小切手はどちら支払いに使えますが、現金に両替えできるタイミングが違います。
手形と小切手の現金化できる日の違い
- 手形は、銀行などに提示しても一定の期間、現金化できません。
- 小切手の場合、銀行などに提示すればすぐに現金化できます。
この違いを意識して実際の問題で仕訳方法の違いをみてみましょう。
最初に手形について
手形の仕訳
A商店は、B商店から商品500円を仕入れ、約束手形を振り出した。
A商店の仕訳を行いなさい。
解答です。
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 仕入 | 500 | 支払手形 | 500 |
同じようにB商店の仕訳を行いなさい。
解答です。
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 現金 | 500 | 売上 | 500 |
次に小切手の仕訳について
小切手の仕訳
A商店は、B商店から商品500円を仕入れ、小切手を振り出した。
A商店の仕訳を行いなさい。
解答です。
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 仕入 | 500 | 当座預金 | 500 |
上の取引きのB商店の仕訳を行いなさい。
解答です。
| 借方科目 | 金 額 | 貸方科目 | 金 額 |
| 現金 | 500 | 売上 | 500 |